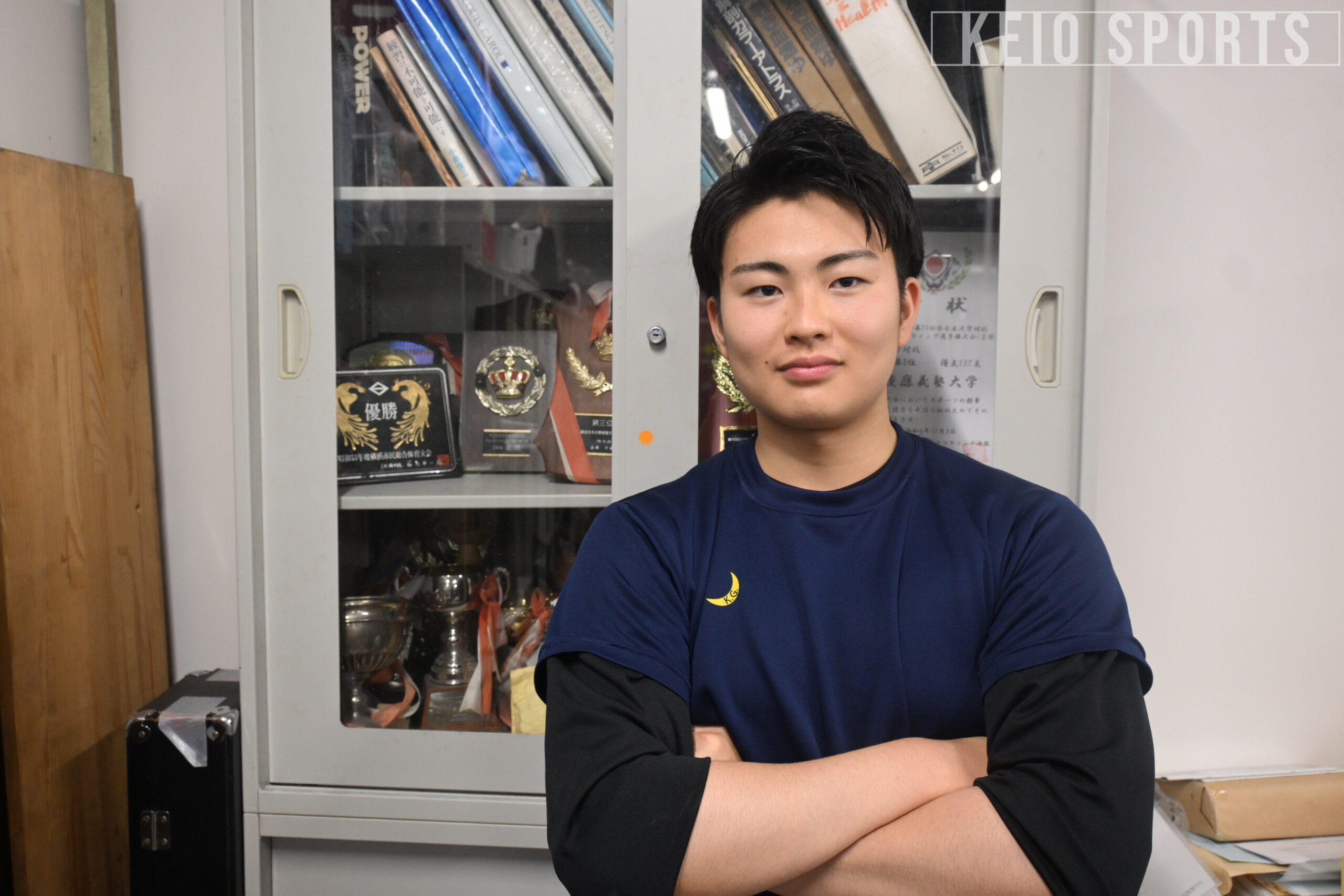慶大の体育会を深掘りしていく新企画、「What is ○○部?」。第26回は重量挙部を取材。今回ケイスポは、日吉キャンパス記念館地下で行われた重量挙部の練習の様子を取材した。
後半は、今年重量挙部を率いる岸田博斗主将(文4・土浦日大)へのインタビューを掲載。今回は「主将から見た」重量挙部の “姿” を探る。
――この部の雰囲気
賑やかですね。みんな大抵は大学からこの競技を始める選手が多いので、そこから切磋琢磨して、「半学半教」というか、互いに教え合って強くなるという雰囲気があります。誰かを中心にという感じではなく、全員で支え合ってみんなで成長してゆく、という雰囲気は代々あるのかなと思います。この賑やかな環境で練習できることがすごく嬉しいです。
――部のスローガンなどはあるか
スローガンですか。1部の大学というのはどこも高校からスポーツ推薦で選手を引っ張ってきます。でも我々慶應義塾にはスポーツ推薦がないんですね。その中で他の大学とどう渡り合うのか。しかもウエイトリフティングはマイナースポーツなので、なかなか高校に部活動が存在しないんです。だから大学からスポーツを始める選手が9割で。他のリーグ1部の大学は多くが高校の時点でトップレベルに立っている選手を集めてくるんです。なので我々は4年という限られた時間の中でいかにどれだけ強くなり記録を伸ばすか、ポテンシャルを引き出して、1部リーグにいる全国の強豪チームの選手にくらいついて渡り合うか、という点が、弊部のスローガンと言わずとも我々重量挙部の掲げるものなのではないかなと思います。

逆境にどう立ち向かうかを力強く語ってくれた
――そうした逆境の中で戦う1部リーグ
去年2部リーグで2位になって1部リーグ昇格を決めた時点で、1部リーグで戦えるような記録、「標準記録」って言うのですが、それを持っている選手が一人くらいしかいなくて。今は標準記録を持っている選手が自分入れて4人いて。この夏で取れるかなって選手も出てきていて。まず1部リーグで戦えるようなチームにこの一年間で育てることが大事だと思っています。
1部リーグにも昇格降格があって、自分らのチームとは比べ物にならないくらい強いチームがまだまだ存在する中で、この一年間全力で強化してどの程度まで喰らいつけるのか。ただ、今年の代は大学以前からこの競技をやっている経験者が少ない中で、成長曲線に目を見張るようなものがあるので、この一年間全力を尽くして、「新しい景色」を見に行くことには間違いなく意味があることだと思います。

練習中は周囲への目配せを怠らない
――重量挙をやっていると筋肉痛になるのではないか。そうなると毎日練習するのは困難ではないのか
練習には、実際にバーベルを上に挙げるような、皆さんが重量挙と聞いて思い浮かべる「試技」と呼ばれるものと、ここの部位を鍛えるって決めてやるような、いわゆる筋トレの「補強」の2種類あります。「重量挙ってことはやっぱ筋トレするの?」とはよく聞かれるんですけど、重量挙って世間で思われているより全身運動で、重いものを馬鹿力で上げるのではなくて、いかに全身を使って効率的に挙げるか、という点を追求したスポーツだと思っています。もちろん全身運動の「試技」をずっとやってると疲れるんですけど、全身運動の「試技」と一部分を鍛える「補強」とを織り交ぜながらやるようにしてて、同じ部位が過度に疲労して壊れるなんてことは起きにくいようになっています。
――重量挙で一番重要になる部位は
脚です、圧倒的に脚です。バーベルって下に置いてあるじゃないですか。みんな腕を使うって考えがちなんですけど、足の反動で上に挙げるんです。なのでまず脚です。脚が弱かったら何もできないです。
――岸田主将は高校から重量挙をやっていると伺った。重量挙を始めたきっかけは
自分もいろんな人にどうしても重量挙を始めたのかって聞くのがすごい趣味なのですが(笑)。聞いて回ってるとみんな意外と偶然始めたみたいな人が多くて。そんな自分も中学までは卓球やっていました。それで高校も卓球やろうと思って高校の体験入部みたいなタイミングで卓球の練習場に行ったら、隣が重量挙の練習場で、そこの先輩と仲良くなって気がついたらそっちに入っていたっていう(笑)。家族にも友人にもすごく驚かれたのを覚えています。なんでお前ウエイトリフティングやってんだ!?みたいな(笑)。

重量挙を始めたきっかけは意外にも偶然だった
――岸田主将が思う重量挙の魅力とは
自分の成長を、すごく実感しやすいところだと思います。例えばチーム戦の競技だとどうしても活躍が客観的に出にくい部分もあると思うんですけど、ウエイトリフティングは個人競技で自分の記録がそのまま数字に出てくるんです。昨日70kg挙げられたものが今日は71kg挙げられたとか、やった分だけ強くなっていきます。そうやって自分の成長が見えるところは良くも悪くもモチベーションの持ち方に関わってきますし、たかが1kgって思われるかもしれないんですけど、その1kgで勝負が決まるので、その1kgを絞り出すためにどうすればいいのかを頭で考えて身体で実践してっていうのを繰り返すのが、この競技の醍醐味なんじゃないかなと思います。
魅力という点で言えば他には、ウエイトリフティングは個人競技である一方で、互いに鼓舞し合いながら試合を戦うという側面があるところだと思います。かつてウエイトリフティングはマイナースポーツと見なされていたので、ここ10~20年は部員がずっと少なかったんですけど、それが平成後期ごろから部員が増えて、今は合計で55人(取材時点)にまでなって、かなり大所帯になりました。自分の高校時代の重量挙部は上級生が7人、自分の学年に至っては自分一人だったので(笑)。薄暗い場所でひっそりと、それでもアツくやっていました。それで大学に入ってから、多くの先輩と同期に囲まれて日々練習をして、それで初めて試合に出た時に、先輩や同期の声援を一身に受けて試技をするって経験をした時に、すごく痺れるものを感じました。個人競技とはいえ集団で戦うという、ウエイトリフティングの持つ側面を初めて垣間見た瞬間でした。
――逆に挫折する経験などは
ありますよ、めっちゃあります(笑)。自分の競技人生の9割5分は挫折ですね。高校時代から自分はずっと怪我が多くて、大学1年の冬にヘルニアをやってしまって、そこから2年生はほぼ練習できなかったりとか、3年生になっても肩とか腰とか手首とか色々なところで怪我をしてきて。大学でここまで3年重量挙をやってきましたが、実際に競技をやっていたのは長さにして1年にも満たないかもしれないです。
すごくめちゃくちゃ悔しかったし、選手を辞めてスタッフに回ろうかと思ったことも何度もありました。結果的に今主将としてやっていますが、怪我というものには常に悩まされてきましたね。

何度も挫折を乗り越えてきた岸田主将
――怪我をしている時の過ごし方は
部位にもよりますが、まずは回復を第一に考えます。自分がヘルニアやった時は本当に痛くて、まずはその痛みを堪えるところからですね(笑)。ウエイトリフティングはフォームが大事なんです。怪我していて練習できない間は、マネージャーがフォームの動画をまとめてくれたファイルを作ってくれているのでひたすら自分のフォームを見たりとか、あとは有名な選手のフォームの動画を見てみたりとかもします。
部のSlackには、誰かから教わったこととか、試合中気づいたこととかを各々が書き込んで、それに誰かがフィードバックしてくれたりとか、競技についてディスカッションできる体制を作っていて。そこでいろいろ頭を巡らせながら自分のフォームを考えてみたりとか。怪我するとリハビリ頑張らなきゃってのもあるんですけど、頭で考える時間も増えると思うので、逆にその頭で考えるところで、スポーツ推薦を導入していて強豪高校の選手を獲得できる強豪大学との差を縮める鍵なんじゃないかなと思います。
――やはり強豪大学の選手は手ごわいか
強豪大学にいるということは基本的に大学以前からウエイトリフティングやっていることがほとんどで、やはり長い期間競技やってるとそれだけ技量もフィジカルも全然違くて。自分は高校から始めましたが、それでも試合会場では同じくらいの身長の選手と比べると自分の体格はもはや、ナナフシか!(笑)ってくらいの細さで。大学から始めた選手は4年間という限られた時間の中だと、どれだけ本気で頑張っても作れるフィジカルも限界があるので、じゃあどうするかって言われたとき、やるべきことはしっかり頭で考えて最短距離で向かうことだと思います。練習の取り組み方にせよ、フォームにせよ自分に合ったやり方を頭で考えてやっていくって作業が大切になると思います。
――最後に主将として、部員とのコミュニケーションなどで心掛けていることなどをお願いします!
どんなに忙しくても時間は作るようにしてます。部員は55人くらいいるのでSlackも鳴り止まないし、これ相談したいとか言ってくれる選手も多いし、分身したいな(笑)と思うくらいですが、たとえ後回しになってしまっても、どこかで絶対に時間は作って相談に乗るようにしています。あとは練習中だと話しかけたりとか、観察はめっちゃしてます。あとは自分も何か困ったなってことがあったら、煮詰まるまで考えるんじゃなくて部員の子たちに聞くようにしています。

「チーム岸田」は新しい景色に向けてひた走る
インタビューでは、強い心と常に周囲に気を配りながら上を目指す体育会を引っ張る主将としての強い心意気が垣間見えた。半世紀ぶりの1部リーグでの戦いを迎えた重量挙部。「新しい景色」に向けて日々の鍛錬は続く。
その1kgをけずりだせ。
(記事、写真:神戸佑貴、取材:中原亜季帆)