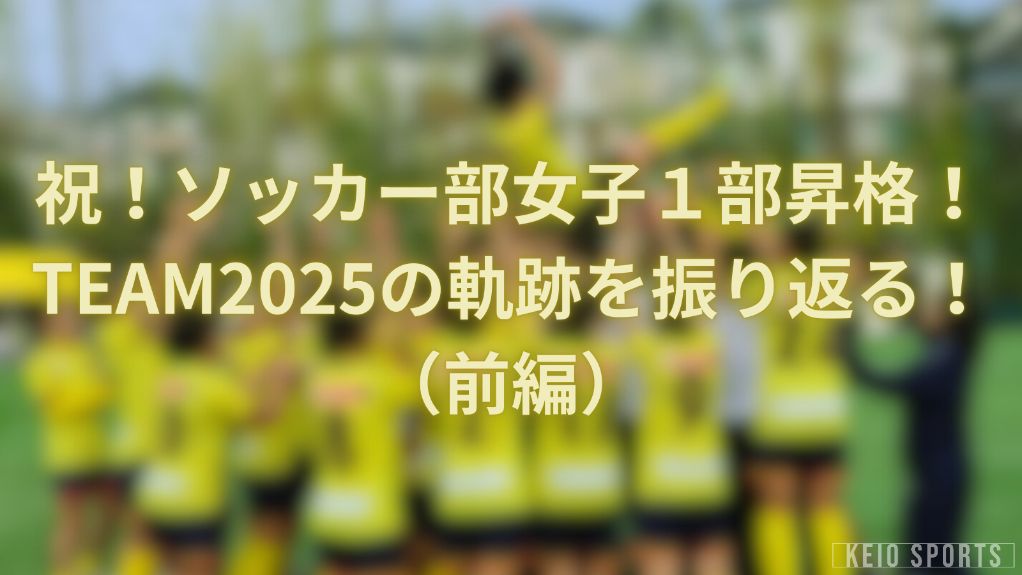今年の予選会にて昨年よりも順位を落とし、総合30位となった慶大。その誤算の一つが、チームの中心戦力となるはずの4年生たちの苦戦だった。経験豊富である彼らがラストランで直面した苦境。その裏では、最高学年、中心選手として背負う責任、近年の慶大競走部長距離ブロックの窮状、様々な要因が彼らを追い詰めていた。
箱根駅伝予選会の激闘を部員たちの証言をもとに振り返る「もう一つの箱根駅伝予選会」(全3弾)。第1弾となる今回は、逆境に耐え、僅かな希望に青春の全てを懸けた長距離ブロック4年生たちの苦闘と、その中で示した確かな足跡に迫る。
「“30位”と知った瞬間に、一気にきました。悔しさと、申し訳なさがバッと出てきて、正直、あれはもう絶望ですよね」
掲示板の端に載った母校の大会結果を見て、主将・東叶夢(環4・出水中央)は言葉を失った。
「『よくやったよな』っていう気持ちはありました。ただ、同時に『俺らのせいだったな』っていう話も、同期とはしてましたね」

「『俺らのせいだったな』って」(東)
全ての大学において、最上級生である4年生はチームの大黒柱。ハーフマラソンの距離を走る予選会では、レースの経験面でも持ちタイムの面でも彼らの重要度は増す。
慶大競走部でもそれは同じ。ハーフマラソンでチームトップのタイムを持ち今回が4年連続の予選会となる東のほか、エース・安田陸人(商4・開成)、今季トラックで飛躍を遂げた鈴木太陽(環4・宇都宮)など経験豊富なメンバー6名が4年生から出走した。
32年ぶりの箱根路へ、母校の悲願を懸けて臨んだラストラン。しかし蓋を開ければ、出走メンバー12名中、4年生の多くはチーム下位に沈んだ。彼らの間に、いったい何が起こっていたのか?

ここで、今年の慶大競走部長距離ブロック・第108代4年生について紹介しておこう。彼らは決して強い世代ではなかった。中高時代に全国大会への出場経験があるのは東を含め数少ない。
その一つ上である第107代は強い世代だった。安倍立矩、田島公太郎、木村有希(いずれも令和7年卒)という実力者3人がチームを支え、彼らの背中を追うように108代も成長を遂げていった。
そんな強い107代が昨年卒業。長距離ブロックは新たな柱を必要としていた。第108代長距離ブロック長には東が就任。出水中央高校時代に、主将として母校を初めて全国高校駅伝へと導いたリーダーシップをかわれての抜擢だった。

リーダーシップをかわれて主将を務めた東
昨年の予選会で総合29位に終わった反省から、生活と練習の両面で改革に着手。睡眠時間の確保など生活リズムを立て直し、学生主体の運営を保ちつつ門限を設けるなどルールを明確化。練習面では、朝練に起伏のあるロードを取り入れ、長い距離で粘る脚力を養った。
こうした取り組みは春の大会で成果を上げ、自己ベスト更新や関東インカレ入賞など成功体験が多くの選手の自信につながった。夏は合宿を見直し、暑さへの順応を重視して日吉での強化練習を実施。
部員数が少ない中、個々の状態を細かく把握し、一人ひとりに合わせた調整を行う体制でチーム力の底上げを図ってきた。
しかし、ここまでチームを引っ張ってきた4年生の多くが今大会の直前には満身創痍の状態だった。
大会2週間前に安田が右足の脛骨を負傷。8月に疲労骨折により長期離脱していた主将の東も、夏合宿を回避するなど1年間十分な練習を積めずにいた。チームの主力を担う鈴木らAチームの選手たちも、怪我のリスクを考慮し別メニューでの調整を強いられた。
「10月の直前期になって痛みが再発して、かなりギリギリでした。大会1週間前の朝がもう本当に痛くて。そのタイミングでコーチに、『今日の練習ができなかったら、走らない方向で』と相談しました。ただ、最終的な判断は僕自身に委ねられていました」(東)

手負いのなか出走を決断
予選会は21キロの長丁場だ。手負いの状態で出走し途中で怪我が悪化したら、最悪の場合だと途中棄権となりチームを窮地に追い込む可能性もある。個人の選手生命が危ぶまれる。
そのリスクを理解していながらも、彼らは出走に踏み切った。この年、慶大長距離ブロックの部員数(スタッフを除いた)は21名と、例年と比べても極めて少ない。このうち予選会に出走するのは12名。例年より遥かに個人のコンディションがチームの戦力に影響する状況だった。“怪我してはいけない”――主力選手であればその不安は計り知れなかったはずだ。
この不安を下級生も感じていた。2年生の弓田一徹(環2・法政二)は当時をこう振り返る。
「東さんは痛みがありながらも走れそうではあったんですけど、安田さんは最後まで出走出来るかわからなくて、二人とも4年生かつ部の幹部で精神的支柱だったんですけど、二人に頼ってばかりではいられないとは考えてました」(弓田)

「二人に頼ってばかりではいられないとは考えてました」(弓田)
欠場しようにも、キャプテンとしての強い責任感がそうさせなかったとも言えるだろう。
「(怪我が)痛くても結局は走っていたんじゃないかなと思います。もちろん、自分が無理をして試合を壊すくらいなら、控えている補欠の選手に託した方が絶対にいい。ただ正直な話、自分が出走しないという選択はあまり想像がつかなかったです」(東)

「痛くても結局は走っていたんじゃないかなと思います」(東)
チームの士気を下げまいとする気概、ラストランへの思い、手負いの主将を休ませる余裕がない今年の慶大の窮状――東主将の言葉からは様々な思いが滲む。
最上級としての責任感――島田亘(法4・慶應志木)もこの宿命と向き合おうとしていた。慶應志木高校陸上部出身。安田や鈴木に比べると自己記録では劣るが、その安定したペースメイク力をかわれ、同郷出身であり中学時代からの付き合いである渡辺諒(法4・慶應)と共にポイント練習ではBチームをけん引。ミドル層の底上げに貢献してきた。

練習を引っ張る島田
1~3年生までは怪我もあり苦悩したが、4年目にして初めて1シーズン怪我無く練習を消化。夏合宿でも全てのメニューをこなしきるなど、確かな自信を胸に最後の予選会に臨んでいた。
「入部当初は完全に夜型の人間だった自分が、4年目の今では朝5時とか早い時では3時台に起きるようになって、エクササイズとかやってる。競走部に入って本当に変わったと思う部分ですね」(島田)
一度はチームを離れていた渡辺も、島田ら同級生の思いを感じ取り、再び陸上に向き合うと、予選会前の9月の猛練習でエントリーメンバー14名に滑り込んだ。
「9月頭のミーティングで、『4年全員で白Kのユニフォームを着よう』という話があったんです。予選会メンバーへの執着が全然なかった自分にとっては、大きなきっかけになりました。島田と最後一緒に走るためにラスト1ヶ月は死に物狂いで調子戻したみたいなところはあるので」(渡辺)

4年の渡辺も滑り込みでメンバー入り
しかし、彼らの積年の思いはあっけなく砕かれることになる。最終結果で慶大は昨年よりも一つ順位を落とし30位。個人順位では、東はチーム9番目、島田と渡辺は10番目・11番目に沈んだ。痛み止めを打ち強行出場した安田は、レース中盤まで好走をみせるも16.4キロ地点で途中棄権となった。
東はレースの大半を痛みをこらえながら戦っていたという。
「5キロ過ぎたあたりからだんだん怪しくなって、痛みはかなり出ていました。そこからは、ストライドを少し小さくするとか、とにかく痛みを抑えて走るしかなかったですね。正直、気持ち的には全然面白くなかったです。スタート前は『いけるかも』と思っていたので、アドレナリンが切れた瞬間に一気に痛みが出て、『なんだよ…』っていう感じで」(東)

「アドレナリンが切れた瞬間に一気に痛みが出て、『なんだよ…』って」(東)
足に痛みが走った瞬間――仲間と話し合って決めたチームの目標、学生連合チームの一員として箱根路を走る夢、あらゆる可能性が遠ざかっていくのを東は感じていた。目標を“個人としての完走”に切り替え、必死に腕を振るしかなかった。
当初はBチームを引っ張るペースメーカーを担う予定だった島田と渡辺も苦戦した。
「入りの5キロは15分30で予定通りでしたが、市街地から公園内にかけての後半はペースを落とす形になってしまいました。ペースを落としてからも、なかなか粘ることができず、自分自身の気持ちの弱さが露呈した結果でした」(島田)

「ペースを落としてからも粘ることができませんでした」(島田)
チームメイトが設定通り走れているのか――レースが進むにつれて不安が募る中、さらに頼みの安田が足を引きずって大きくペースダウンするという出来事が追い打ちをかける。主将の東は必死だった。
「『あれ、ちょっとまずいんじゃないか』と感じた部分はありました。これはもう自分が上げていくしかないなと察しました。途中で金丸さん(蒼=医5・国立)が追いついてきてくれたので、『これは2人で上げていこう』と話して、一緒にペースを上げていきました」

主将の東(右)は金丸(左)と前を追った
練習だったら止めていたかもしれない痛みだった。だが、東にしても島田にしてもチーム10番以内にいる状況であり、自分の1秒がそのままチーム順位に直結する。諦めるわけにはいかなかった。1秒を削る気持ちで最後まで走り続けた。
それでも、やっぱり4年生たちは頼れる存在だった。安田と共に序盤から攻めの走りをみせた鈴木は、個人全体100番以内を射程にとらえる位置でレースを進め、10キロをチームトップで通過。その後、公園内でペースを落とすも、1時間5分18秒で自己ベストを40秒近く更新し、チーム2番手でフィニッシュ。4年生としての役割を果たした。

チーム2位の走りを見せた鈴木
ともに予選会を走った3年生の芦野清志郎(理3・高田)はある先輩のエピソードを口にした。
「レース中、公園内の一番きつい場面で関口さんと二人で並んで走る場面がありました。『関口さんがこれだけの覚悟で前を走っているんだから、自分がここで引くわけにはいかない』と強烈に思わされましたね」(芦野)
関口功太郎(経4・宇都宮)の持ち味は後半の粘りだった。昨年の箱根予選会でも後半に順位を上げチーム3位、今年の関東インカレ1部ハーフマラソンでも4年目にして自己ベストをマークしていた。チームに一人はいてほしい存在である。

最後の大会に臨んだ関口
そんな関口も最後の予選会の直前までは怪我に苦しみ、別メニューでの練習でなんとか本番に向けて調整してきた。決して万全な練習が積めていたとはいえない。それは後輩の芦野ももちろん知っていた。だからこそ、レース当日の先輩の姿が強く印象に残る。
「関口さんは不安な素振りを一切見せず、スタートから攻めの走りを見せてくれました。その姿にまず圧倒されました。一緒に走っている時も、前を走ることで引っ張り、並走することで『お前も来い』と背中を押してくれている。あの瞬間の関口さんの走りこそが、今の僕の理想の先輩像そのものでした」(芦野)

「『お前も来い』と背中を押してくれた」(芦野)
関口は、大会前のインタビューで慶大長距離ブロックの存在についてこう語っていた。
「支え合う存在かなと思っています。自分も苦しい時期にいろんな人に支えられてきましたし、逆に苦しんでいる人に声をかけることも意識していたので」(関口)
東や安田ら4年生のレース後の振る舞いから、芦野は“最上級生としての覚悟”を感じたという。
「レース後の安田さんや東さんは、まともに歩けないほど消耗しきっていました。そこまで自分の体がボロボロになるまで追い込める強さを目の当たりにして、シンプルに『ここまでやるんだ』『自分もそうなるまで走らなければいけないんだ』と衝撃を受けましたね」(芦野)
レース後の慶大競走部による全体ミーティングの場には、周囲の前では涙を見せないように必死に堪えようとする東の姿があった。主将として計り知れない悔しさがあったはずだ。背負っていたものの重さ、悔しさを飲み込むその強さは、後輩たちの目に焼き付いている。
「東さんの表情からは、個人としての感情以上に「チームの顔」として踏みとどまろうとする、4年生としての本当の覚悟を見た気がします」(芦野)

試合後の全体ミーティングでの東
今大会でチーム1位の走りを見せた田口涼太(政2・慶應志木)にとってもその存在は特別だったようだ。
「僕、東さんのチーム、めっちゃ好きだったんですよ。東さんとは同じ部屋で、東さんが部屋長で、自分は部屋子みたいな感じで普段から色々お世話になっていたので、レース後に会った時はもうボロ泣きしましたね。その時、『これから頑張れよ!』っていう言葉とか、今後に向けた励ましをたくさんもらって、すごく印象に残っています」(田口)
一方、当の東本人は複雑な思いを抱いていたという。
「 下級生はすごく頑張っていて、一方で上級生はなかなか力を出し切れなかった。だからこそ、上級生として暗い顔をするわけにもいかなくて、『お前らすごかったな』と声をかけるんですけど、下級生の方は下級生でかなり悔しさを抱えていそうで…チーム全体の感情がうまく共有しきれていないような、少しちぐはぐな空気はありましたね」(東)

「少しちぐはぐな空気はありましたね」(東)
4年生が力を発揮しきれなかった今年の予選会。その要因は何処にあるのか?
自分たちの出来だけを見てやってきた部分があった――東は競走部での自らの4年間を振り返る。
「『自分たちはいける』という自信はありましたが、それは内側だけの話で、目標設定や道筋をもっと客観的に捉える必要があったと思います。慶應としては強度が高い練習ができていたとしても、他大学はそれ以上だったかもしれない。想像以上に他のレベルは高く、自分たちの認識は甘かったんだなと」(東)

「自分たちの認識は甘かったんだなと」(東)
2年生にして今回の予選会でチーム3番手に入った弓田は、最上級生がゆえの重圧に言及する。
「安田さんと東さんと太陽(鈴木)さんは、多少痛くても走らないといけないっていうプレッシャーがあったと思ってて、そこでAチームの人数の少なさってところで余計にプレッシャーがかかっていたと思うので、もっと周りが4年生に頼りきることが無ければ故障もなかったのかなとは思います」(弓田)
今年のBチームは、島田や渡辺ら4年生が常に練習を引っ張っていたという。4年生に頼り切りでいては、その分上手くいかないレースで全員が影響を受けてしまう可能性も高くなる。Bチームで彼らの背中を追い続けてきた2年生の石野は意気込む。
「練習においては、もっと下からの押し上げがあってもいいと思います。自分も、今年渡辺さんや島田さんがBチームでしてくれたように、『この先輩についていけば大丈夫だな、結果が出せるな』と後輩が思ってくれるような存在になりたいです」(石野)

Bチームを引っ張ってきた渡辺
では、4年生たちが部に残したものは何だったのか?
「キツイ練習をやり切った時に、4年生が当たり前のように『ナイス!』と褒めてくれたことが、何よりも自分の中に残っています。 先輩が自分の頑張りをちゃんと見ていてくれることが素直に嬉しかったですし、その積み重ねがあったからこそ、予選会のような大きな舞台でも『自分はやってきた』という自信を持ってスタートラインに立てたのだと感じています」(芦野)
特別な言葉は必要ない。普段の何気ない行動・言動が人の心に残り、支えとなることもある。実力だけでなく、精神的に寄り添ってくれる存在こそ4年生なのかもしれない。
簡単な言葉では片付けられないほどの重い「責任」を背負い、彼らは苦境に立つチームを引っ張ってきた。
そんな彼らのラストランの記憶をここに残しておこうと思う。昨年の予選会で味わった絶望、強い先輩方の卒業、チーム崩壊の危機、部員数の減少、夏合宿の規模縮小――多くの困難を乗り越え、4年間走り切ったのだから。

(記事:竹腰環、取材:吾妻志穂、片山春佳、竹腰環、中原亜季帆、野村康介、森田紗羽)